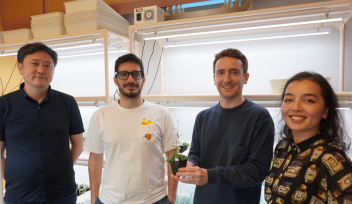複数の生態に適応するために、ゲノムを大きく拡張しているキノコを発見

この度、学術誌『CellGenomics』で発表された数種類のクヌギタケ属(Mycena)の研究で、これらのキノコが予想以上に大きなゲノムを持つことが判明しました。これまでキノコは純粋な腐生性、つまり死んだ有機物を分解することだけで生きていると考えられていましたが、今回の発見により、状況の変化に応じて異なる生態へ適応可能な遺伝子を備えている可能性が示唆されました。特に、北極圏に生息するクヌギタケ属の一部は、これまでに報告されたキノコの中でも最大級のゲノムを持つことが分かりました。
これらのキノコは、ゲノム全体が広範に拡張しています。これには、植物への侵入や相互作用、炭素の分解を助ける遺伝子だけでなく、まだ機能はよく分かっていないけれども重要である可能性が高い遺伝子も含まれています。さらに、他の無関係な菌類から水平伝播によって獲得した繰り返し非コード要素や遺伝子も多く存在します。
「クヌギタケ属のサンプルは北ヨーロッパで採取され、共同研究者の一人が北極圏からサンプルを集めました。そのうちの3種の塩基配列の解読に成功し、これらの北極圏の種は、通常のクヌギタケ属に比べて著しく大きなゲノムを有していることが分かりました」と沖縄科学技術大学院大学(OIST)進化・合成生物学ユニットの宮内慎吾博士は説明します。「このようなことは通常ありえない、というのが私の最初の印象でしたので、共同研究者に連絡を取り、ゲノムアセンブリが正しいかどうかを検証してもらいました。そして、これらの高度に拡張されたゲノムは、北極圏の特定のクヌギタケ属に特有のものであると結論づけました。」

「進化論によれば、生存に有利でない形質は時間とともに失われる傾向があります。従って、このような大きなゲノム構造による適応性と汎用性は、これらの菌類にとって有利であるに違いないのです」とフランス国立農業・食糧・環境研究所(INRAE)とロレーヌ大学のFrancis Martin教授は付け加えます。「大きなゲノムを持つということは、不必要と思われる機能をたくさん持ち、細胞分裂のたびに複製されなければならないという労力がかかってしまいますが、それにもかかわらず、大きなゲノムを持っているのです。これは、植物にも見られるように、北極のような極限環境では特にそうなのかもしれません。」
研究チームは、森林生態系において落ち葉などの主な分解者としてのキノコの役割に基づき、クヌギタケ属の研究に着手しました。クヌギタケ属は、その小さな子実体にもかかわらず、世界の炭素循環において重要な役割を担っています。この種類のキノコは、長い間、純粋に死んだ有機物を食べて生きていると考えられていましたが、最近になって、いくつかの種は生きている植物との共生的または寄生的な相互作用によっても生存していることが分かりました。また、クヌギタケ属は生物発光という暗闇で光る性質を持っており、5種のクヌギタケ属のゲノムを研究した論文が以前ありました。研究チームは今回、これらの生態についてさらなる理解を深めるために、生息環境に対する嗜好性が異なる幅広い種類のクヌギタケ属について研究しました。
本研究では、クヌギタケ属24種と、Atheniella floridulaとして知られる近縁種6種、北極圏の3種に加え、クヌギタケ属以外も含む計33種のゲノムを比較しました。進化の過程でゲノムがどのように進化・拡大したのか、また、生態によって植物細胞壁溶解酵素がどのように異なるのかを理解しようと試みました。
その結果、驚くことに、クヌギタケ属で全体として大規模なゲノム拡大を示し、想定される生態に関係なく、すべての遺伝子ファミリーに影響が及んでいることがわかりました。この拡大は、新規遺伝子の出現だけでなく、遺伝子の重複、多糖類を分解する酵素を作り出す遺伝子のコレクションの拡大、ジャンピング遺伝子(トランスポーザブル・エレメント)の増加、他の菌種からの遺伝子の水平伝播などによってもたらされたと考えられます。また、北極圏で採集された2種のゲノムの大きさは、温帯に生息する菌類の2〜8倍と、圧倒的に大きいことも分かりました。
研究チームは、北極圏に生息する2種のゲノムが、一般的なクヌギタケ属のゲノムを大きく超えて拡大していることに特に驚きました。さらに、クヌギタケ属が遺伝子の水平伝播によって子嚢菌の遺伝子を獲得していることも発見しました。これらの種は温帯地域にも生息していますが、サイズが大きいのは特定の種の特性によるものなのか、それとも北極圏の環境に関連した影響なのかは不明です。
しかし、いくつかの北極圏の植物は、温帯地域の近縁種と比較して、トランスポーザブル・エレメントでゲノムを膨張させたり、単にゲノム全体を完全に複製したりすることが示されており、北極圏のキノコでも同様の並行進化が起こっている可能性があります。
「一般に、分解菌から共生菌への進化的移行は、数百万年前の進化の過程で、いくつかの菌類群で並行して起こったと考えられています」とノルウェーのオスロ大学のHåvard Kauserud教授は話します。「しかし、クヌギタケ属では、この漸進的なプロセスが目の前で起こっているように見えるのです。」
「他の研究から、他の菌類とは異なり、クヌギタケ属が複数の生態を選択できることが明らかとなっています。今回の発見は、こうした複数の生態が選択可能であることがゲノム構造にも反映されていることを示唆しています」と共同筆頭著者のオスロ大学のChristoffer Bugge Harder博士は話します。
本研究は、ゲノム配列だけから生物の習性を理解しようとする研究にも重要な示唆を与えています。
データサイエンティストで、アートにも強い関心を持つ宮内博士は、データの可視化を工夫することが楽しいと語っています。「この研究は2年間かけて菌類のゲノムの特徴を比較しました。そこで小さなキノコの色に着想を得ました。私が作成した図は、19世紀フランスの印象派の画家、ピエール=オーギュスト・ルノワールに影響を受けたものです」宮内博士は現在、森林菌類とは大きく異なる希少な深海菌類のゲノムを解読するプロジェクトに取り組んでいます。「私たちの目標は、珍しい遺伝子、酵素、代謝産物を発見するためのゲノムマイニングです。最終的には、バイオテクノロジー応用のためのユニークなゲノム物質を単離することを目指しています。小さなキノコに秘められた大きな可能性を多くの方が認めてくださり、研究資金面でも支援を継続的に得ることができればいいと思っています」と宮内博士は話します。

本記事は、出版社 Cell Press が発表したプレスリリースの内容をもとに、OISTサイエンスライターのマール・ナイドゥが編集したものです。
論文情報
研究ユニット
広報・取材に関するお問い合わせ
報道関係者専用問い合わせフォーム